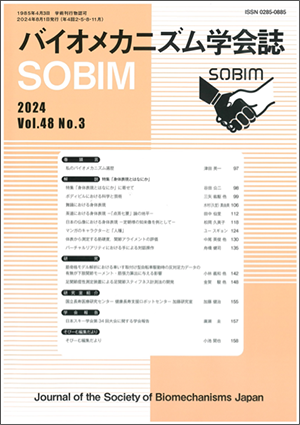お知らせ 2024.10.31 2024年度 教育・研究活動 報告
田村優樹先生、鴻崎香里奈先生、中里浩一先生の原著論文がThe Journal of Physiologyに掲載されました。
- タイトル
- Monocarboxylate transporter 4 deficiency enhances high-intensity interval training-induced metabolic adaptations in skeletal muscle
- 著者
- Yuki Tamura, Eunbin Jee, Karina Kouzaki, Takaya Kotani, and Koichi Nakazato
- 掲載雑誌
- The Journal of Physiology, Volume 602, Issue 7, 1313-1340, 2024.
概要
「運動中に骨格筋に過剰に乳酸を蓄積させた場合、トレーニング効果に影響するのか?」という問いを検証しました。この問いを検証するために、「骨格筋から血液に乳酸を放出する輸送体(MCT4)を欠損させたマウス」を開発し、高強度トレーニングを実施させました。
その結果、骨格筋に過剰に乳酸を蓄積させながらトレーニングを実施することで、高強度運動時の持久力が一層向上することを明らかにしました。その分子メカニズムとして、「解糖系によるATPおよびピルビン酸産生能力が向上すること」および「ピルビン酸をミトコンドリアでATPに変換する能力が向上すること」も併せて見出しました。本研究により、骨格筋の乳酸濃度を高めることは、より高いトレーニング効果を得るための戦略となる可能性が示唆されました。
田村優樹先生が執筆担当された「ミトコンドリアトレーニング 〜筋肉中心で考えるトレーニングサイエンス」が出版されました。
- タイトル
- ミトコンドリアトレーニング 〜筋肉中心で考えるトレーニングサイエンス
- 編著者
- 八田秀雄
- 著者
- 榎木泰介、加藤弘之、北岡祐、髙橋謙也、高橋祐美子、竹井尚也、竹村藍、田村優樹、寺田新、星野太佑、増田紘之、松永裕、見寺(吉田)祐子、向井和隆
出版情報
- 出版社
- 市村出版
- 発売日
- 2024年5月9日
- ISBN-10
- 4902109670
- ISBN-13
- 978-4902109672
概要
トレーニングによる骨格筋のミトコンドリアの適応に関わる書籍の中で、第二章(量的制御の分子メカニズム)の執筆を担当した。
2章 トレーニングによる骨格筋ミトコンドリアの量的制御 田村 優樹
- はじめに:なぜ,トレーニングによる適応のメカニズムを分子レベル・細胞レベルで理解することが重要なのか?
- 骨格筋のミトコンドリアの量や機能を高める生理的意義:なぜ骨格筋のミトコンドリアの量・機能を高めることが必要なのか?
- 遺伝情報(DNA)から身体の部品(タンパク質)を作り出す仕組みの基礎
- トレーニングによって骨格筋のミトコンドリアの量が増加する分子メカニズム
- ミトコンドリアの分解と分子メカニズム
田村優樹先生、鴻崎香里奈先生、中里浩一先生の原著論文がAmerican Journal of Physiology – Cell Physiologyに掲載されました。
- タイトル
- Coculture with Colon-26 cancer cells decreases the protein synthesis rate and shifts energy metabolism toward glycolysis dominance in C2C12 myotubes
- 著者
- Yuki Tamura, Karina Kouzaki, Takaya Kotani, and Koichi Nakazato
- 掲載雑誌
- American Journal of Physiology – Cell Physiology
Volume 326, Issue 5, C1520-C1542, 2024.
概要
がんに伴う骨格筋萎縮・機能不全(がん悪液質)は、直接的な死因となるほか、化学療法の効果低減、QOLの低下の原因となります。がん悪液質の治療法を開発のためには、第一に、がん悪液質の病因・病態解明が必要不可欠です。しかし、がん悪液質の病態は、多臓器間、多細胞間の極めて複雑な時空間的な相互作用の結果であり、その解明は容易ではありません。本研究では、大腸がん由来上皮細胞と骨格筋由来細胞の非接触共培養の実験モデルを構築し、がん細胞と骨格筋の直接的なクロストークを解き明かすことを目的としました。その結果、大腸がん細胞との共培養によって、骨格筋のタンパク質合成能力の低下、エネルギー代謝がミトコンドリアでの酸化的リン酸化から解糖系優位にシフトすることを見出しました。本研究で得られた知見は、癌悪液質の病因・病態の深い理解、治療法の開発に寄与することが期待されます。
三矢紘駆先生、岡田隆先生の解説がバイオメカニズム学会誌に掲載されました。
- タイトル
- ボディビルにおける科学と芸術
- 著者
- 三矢 紘駆、岡田 隆
- 掲載雑誌
- バイオメカニズム学会誌
Vol。48、No。3、99-105、2024
概要
ボディビルとは、主にウエイトトレーニングによって鍛え上げた肉体が主観的に審査される審美系競技である。競技会では、主に筋肥大(バルク)、絞り(除脂肪)、バランス、ポージング(プレゼンテーション)などの要素から総合的に審査されるものであり、筋肉量や体脂肪量といった定量評価可能な項目の客観審査ではない。様々なトレーニング技術、栄養管理方法を駆使して、自らが理想とする肉体を追求し続けるボディビルダーは、競技者であり、科学者であり、芸術家である。特に、隣接しあう筋群内で領域特異的に、またひとつの筋を長軸区画的に細かく鍛え分ける技術、さらに体脂肪を極限まで僅少化する食事術はボディビル特有の技術であり、それらの解明には学術的な価値があり、また様々な状況に応用可能な社会的価値を有するものである。本解説ではボディビルの理解を共有すべく、ボディビルで求められる要素を中心に、歴史や各カテゴリーの特徴まで、幅広く説明する。