
保健医療学部
体育スポーツの専門性を備えた医療の担い手となり、
柔道整復師・救急救命士として国民の健康と生命を守る。
柔道整復師・救急救命士として国民の健康と生命を守る。
目指す人物像
保健医療学部を構成する整復医療学科と救急医療学科の学生が共通して目指すのは、高い倫理観、科学的根拠に基づく思考力、グローバル化に対応できる多様性と国際性を身につけた医療人です。保健医療学部共通科目での学びを通して語学、教養、科学そして体育の基礎を修得した上で各学科の専門性に応じた高度な医学的知識・技術を身につけます。
習得すべきスキル
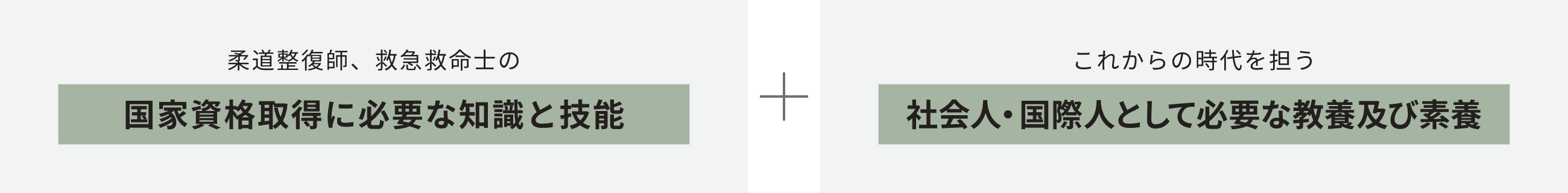
学部長メッセージ
高度な医療知識・技術を備えた医療人として、グローバル社会に貢献できる人材を育成する
整復医療学科では柔道整復師(国家資格)、救急医療学科では救急救命士(国家資格)として医療貢献すべく、責任ある仕事に就いていきます。
本学保健医療学部では、日本を代表するトップ教授陣により、科学的根拠に基づいて的確な判断ができる能力と高度な医療知識・技術のみならず、人の痛みがわかる思いやりと優しさを兼ね備えた医療人の育成を行ってまいります。
保健医療学部長 中里 浩一
本学保健医療学部では、日本を代表するトップ教授陣により、科学的根拠に基づいて的確な判断ができる能力と高度な医療知識・技術のみならず、人の痛みがわかる思いやりと優しさを兼ね備えた医療人の育成を行ってまいります。
保健医療学部長 中里 浩一

保健医療学部が定める3つの方針
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
アドミッション・ポリシー(入学者受入の方針)
保健医療学部の特長
整復医療学科
骨折や脱臼、捻挫や肉ばなれなど日常生活やスポーツで発生する怪我を治療するスペシャリストを育成
怪我の応急手当からリハビリテーションまでを専門とする柔道整復師(医療国家資格)の取得、さらに競技復帰や再発防止をもサポートできるトレーナーとなるための知識と技術の修得を目標とします。日本体育大学の特徴を生かし最先端のトレーニング科学やスポーツ科学も学びます。こうした柔道整復学とスポーツ関連科学を学ぶことにより、「スポーツやトレーニングを熟知した柔道整復師」や「怪我の治療ができるトレーナー」の養成を目指します。臨床実習
日体大のアスリートを中心とした多くの患者さんが来院する横浜・健志台キャンパス内に設置された「日本体育大学スポーツキュアセンター」で臨床実習を行います。また、スポーツ現場での臨床実習も実施します。
野外活動実習
1年生の7月に高原で野外活動実習を行います。実習では酸素の薄い高地でジョギングなどの運動を行って高所トレーニングを体験するとともに、運動中の動脈酸素飽和度などの生理的指標を測定・分析することでトレーニングの理論を学びます。
海外整復医療総合実習
柔道整復の技術を活かし、世界で活躍することを目指すためには欠かせない実習です。アメリカ現地で、各種プロ競技やトレーニング施設で活躍するメディカルスタッフやスポーツ指導者等から最新のトレーナー事情や実技を学び、プロ競技の試合観戦とその舞台裏も見学します。
資格取得について
整復医療学科では以下の資格等が取得可能です。- 柔道整復師(国家試験受験資格)
- 日本スポーツ協会共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ受講・試験免除
- 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(受験資格※)
- 日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者(受験資格)
- 社会福祉主事(任用)
(GPAとはGrade Point Averageの略で、成績評価制度のことです)
救急医療学科
将来、プレホスピタルケアにおいて、指導的立場の救急救命士になって活躍する。
専門教育を生かす充実した教養科目と高名な指導者からの真の専門教育の実践。
“充実した教育力”を誇る救急医療学科。
救急医療学科では、長年日本の救急医療を牽引している指導医、専門医、指導救命士から直接教育指導が受けられます。崇高な精神を学ぶ人体解剖学実習の実施、実際の救急現場活動を体感できる少人数によるシミュレーション実習、日本全国での救急車同乗実習や多施設における救急指定·臨床指定病院、救命救急センターで充実した実習を実施します。他を凌駕する“人間力を育成” する多彩なイベントを豊富に用意しています。専門教育を生かす充実した教養科目と高名な指導者からの真の専門教育の実践。
“充実した教育力”を誇る救急医療学科。
救急医療学科の3本柱
1.救急医療
 【実践的なシミュレーション実習】
【実践的なシミュレーション実習】
豊富な臨床経験と教育にたける救急医療の専門家から、すべて感染症対策を学んで行われる実際の救急現場を完全想定したシミュレーション実習。
 【世界初! 先進的ハイブリッド実習】
【世界初! 先進的ハイブリッド実習】
世界で最初に現実の救急現場をVR(Virtual Reality)教材で作成。非対面講義でも実習の質を維持している。先進的な実習を展開。
2.蘇生医療
 【世界最高の救急医療を学べる貴重な実習】
【世界最高の救急医療を学べる貴重な実習】
米国シアトル市で救急現場の第一線で活躍するワシントン大学HARBORVIEW MEDICAL CENTERMedicOneのParamedicを毎年招いて、最先端の蘇生医療の知識と技術指導が受けられます。
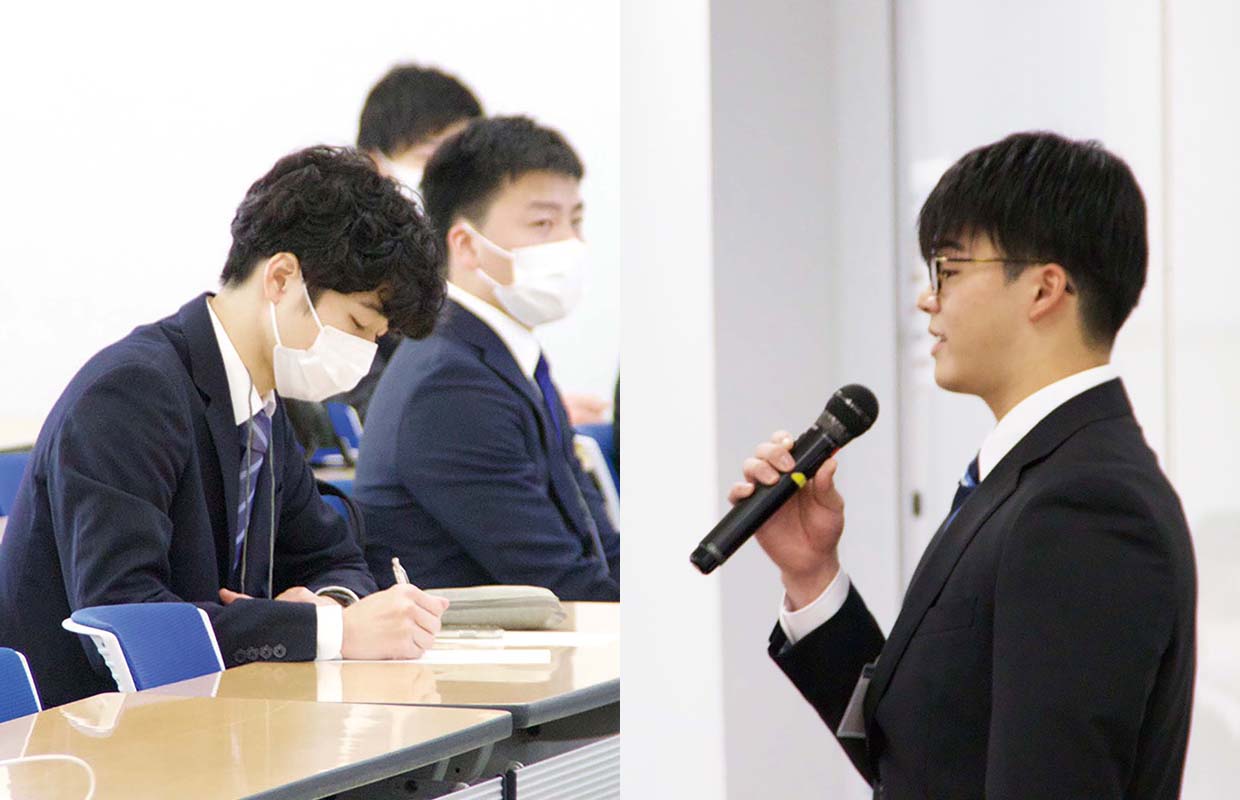 【Challenge! 救命蘇生研究会】
【Challenge! 救命蘇生研究会】
毎年消防と医療機関、保護者、卒業生を招いて日体onefamilyになり救急医、救急救命士、学生からの学術·研究発表を実施。自ら体験したイベント内容を1年生から発表しています。知識の修得だけでなく、コミュニケーション能力の向上につながっています。
3.災害医療
 【災害医学の専門家による講義】
【災害医学の専門家による講義】「災害医学」の講義では、国内外で活躍してきた著名な専門家からの講義を受けることができます。
 【資格取得! 防災減災対策演習】
【資格取得! 防災減災対策演習】
日本防災士機構の定めるカリキュラムに則り、「自助」「共助」「協働」を原則とした、防災士の資格取得を目指します。防災士資格取得者:2019年度34名 2020年度40名。
それぞれ世界の情勢をふまえて指導できる救急救命士の育成
一人でも多くの「失われずにすむ命」を救い、「その家族の生活」を守りたい。人命救助によって得られた決して絶えることのない“誇らしい満足感” が待っている。
救急医療学科 学科長 小川理郎 教授



授業Pick up
医療英語Ⅰ
 医学・医療に関連する英語力を養う
医学・医療に関連する英語力を養う
医療現場で使用される英語の意味や定義、その背景にある医学情報や医学・医療知識の基礎について、英語テキストの読解を通して学修します。一見難しそうな医療英単語ですが、そのほとんどは複数の語が結合してできており、語源がわかれば大きなヒントになります。
医学概論
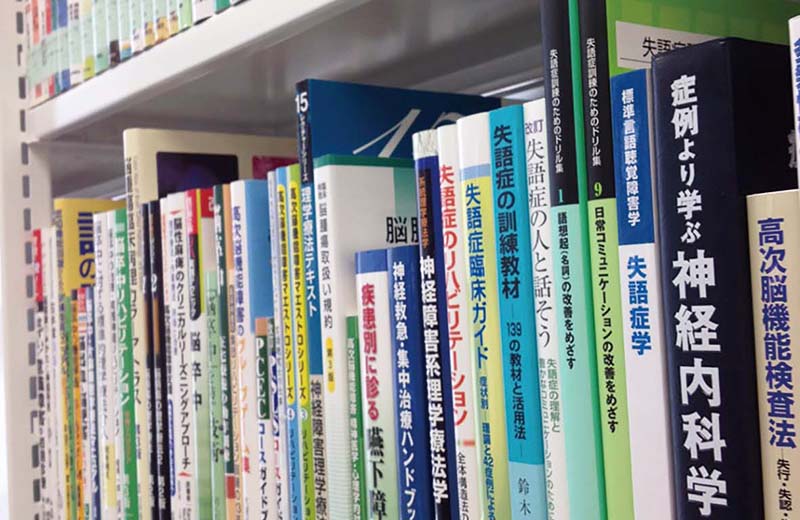 医学の理解に必要とされる生物学の基礎を学修
医学の理解に必要とされる生物学の基礎を学修
健康とは何か、医療の本質、医学・医療は誰のものか、医の倫理、生命倫理、患者の人権、死生観、医療従事者に求められるもの、日本の医療システム、ヘルスプロモーション、医療事故と医療裁判、医療と科学技術等、医療に関わる様々な現代的課題から医療の本質を学びます。
基礎細胞生物学
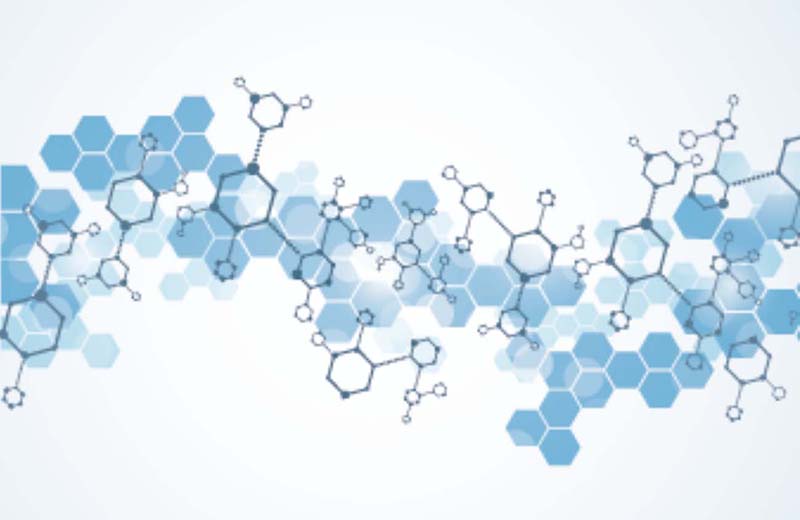 次世代医療において細胞生物学の理解は必須
次世代医療において細胞生物学の理解は必須
細胞を基盤とした再生医療が次世代医療の中核とされている現代、細胞生物学の理解は医療従事者には必須です。本学修ではまず細胞と遺伝情報の関わりなどを概観、次に細胞分裂など多細胞系の理解を、最終的には細胞を基礎とした個体の生理学的理解の学修を目指します。
保健医療学部共通カリキュラム